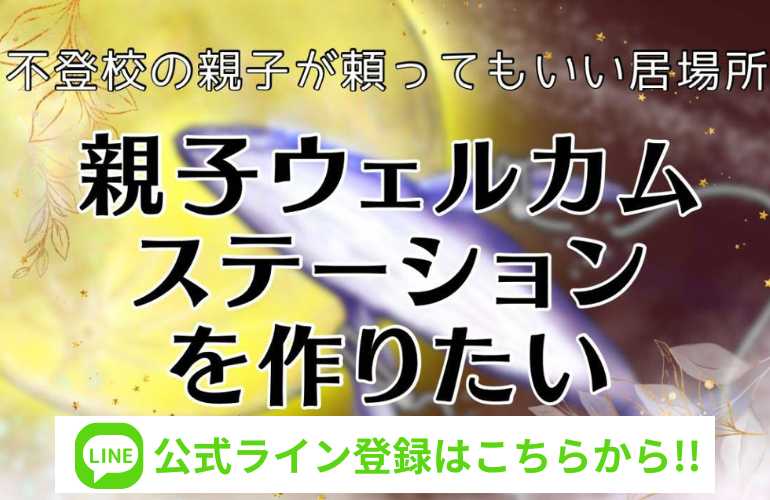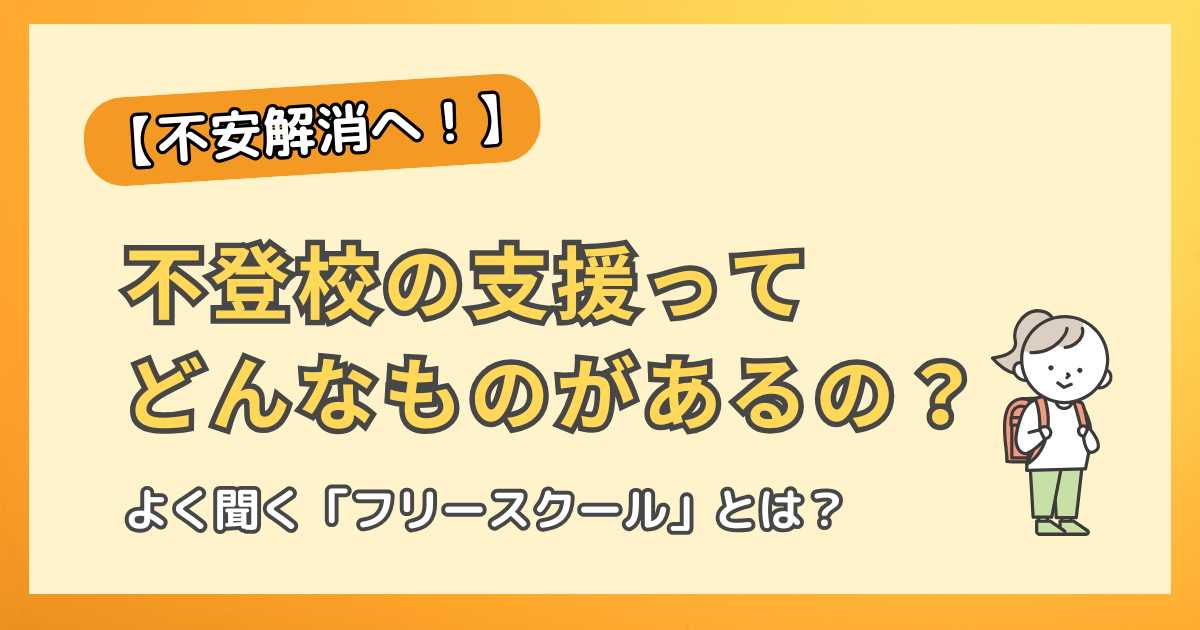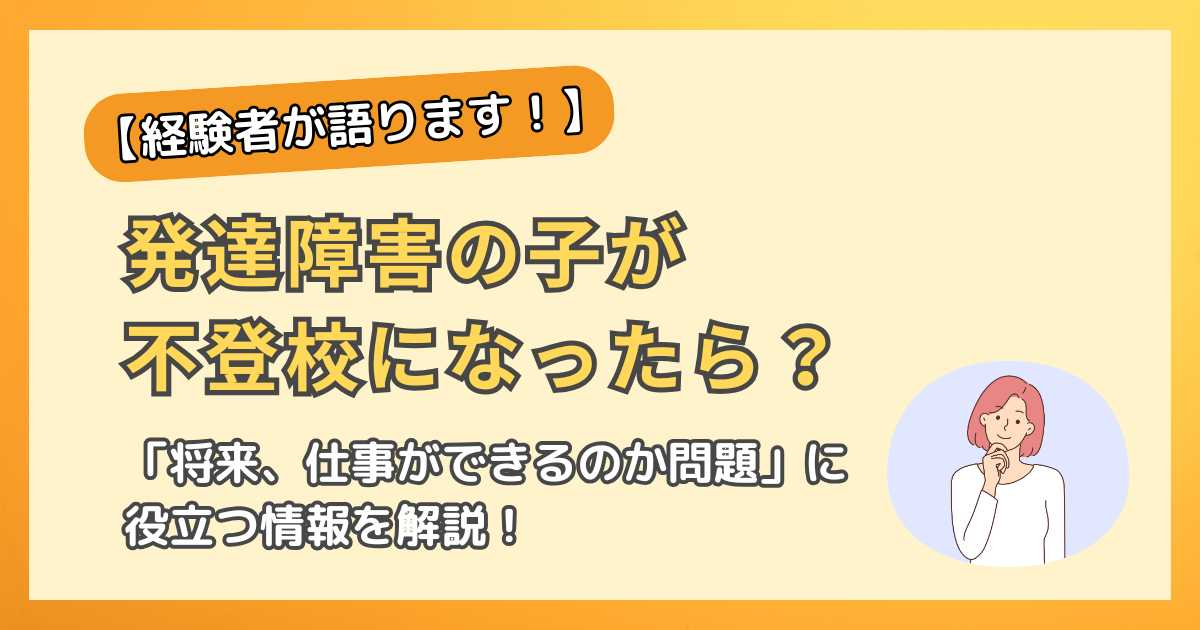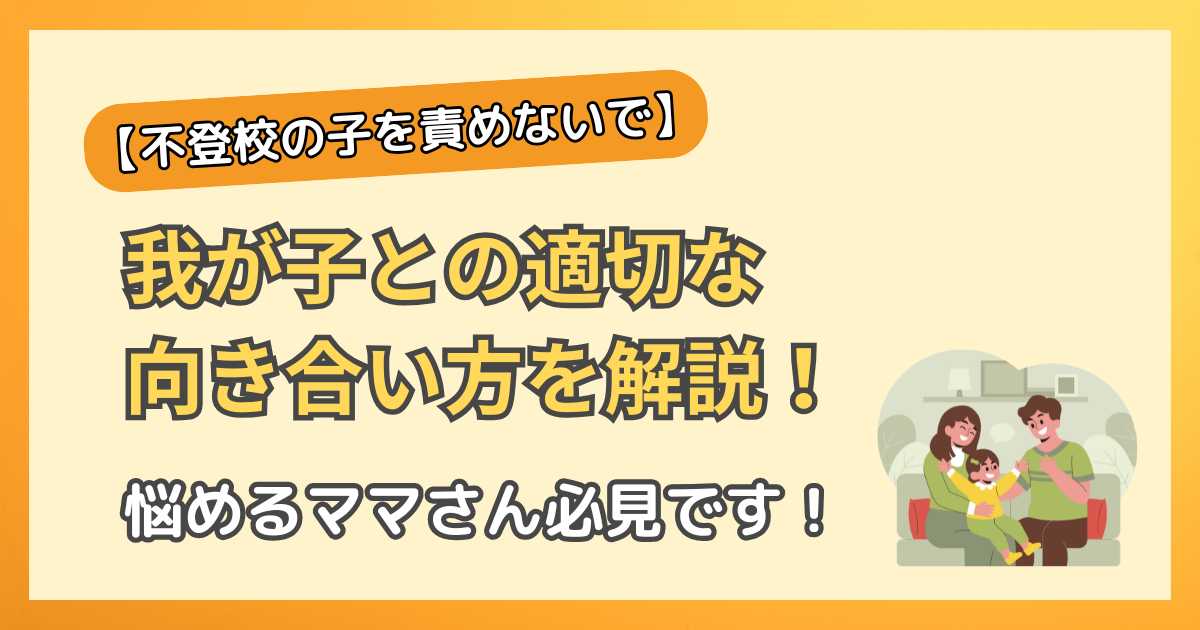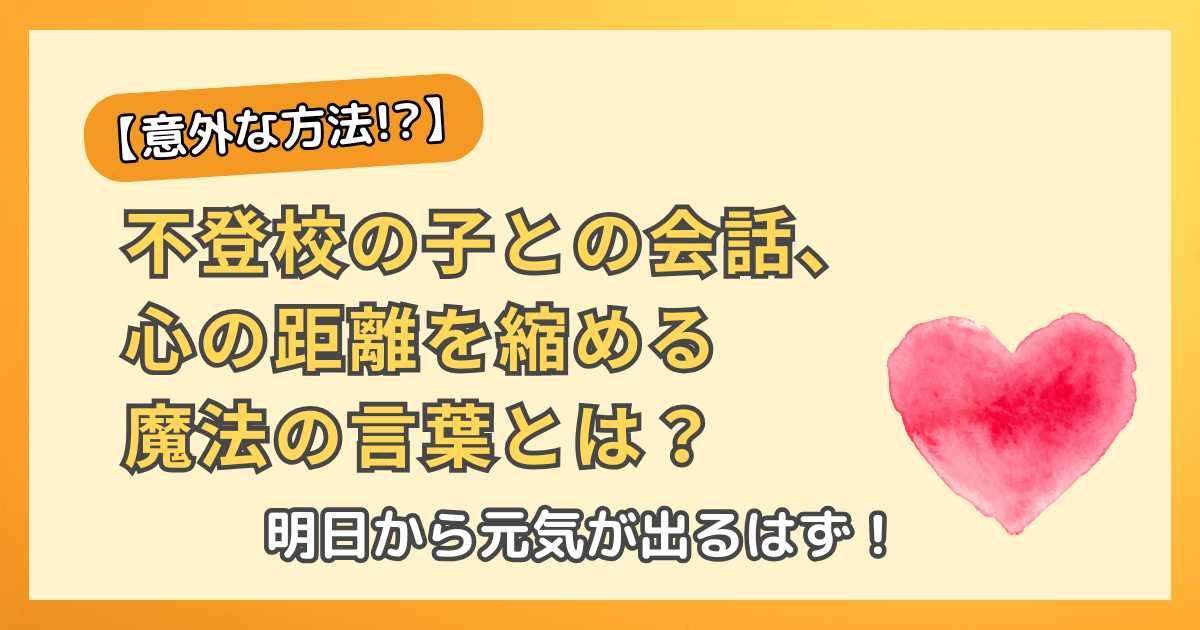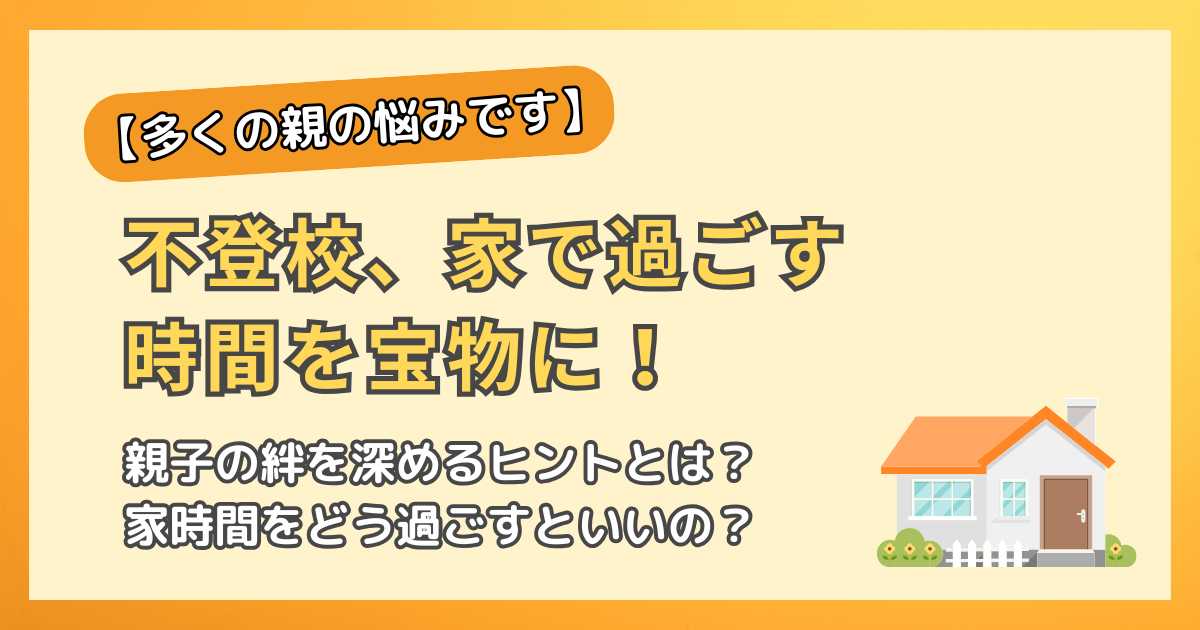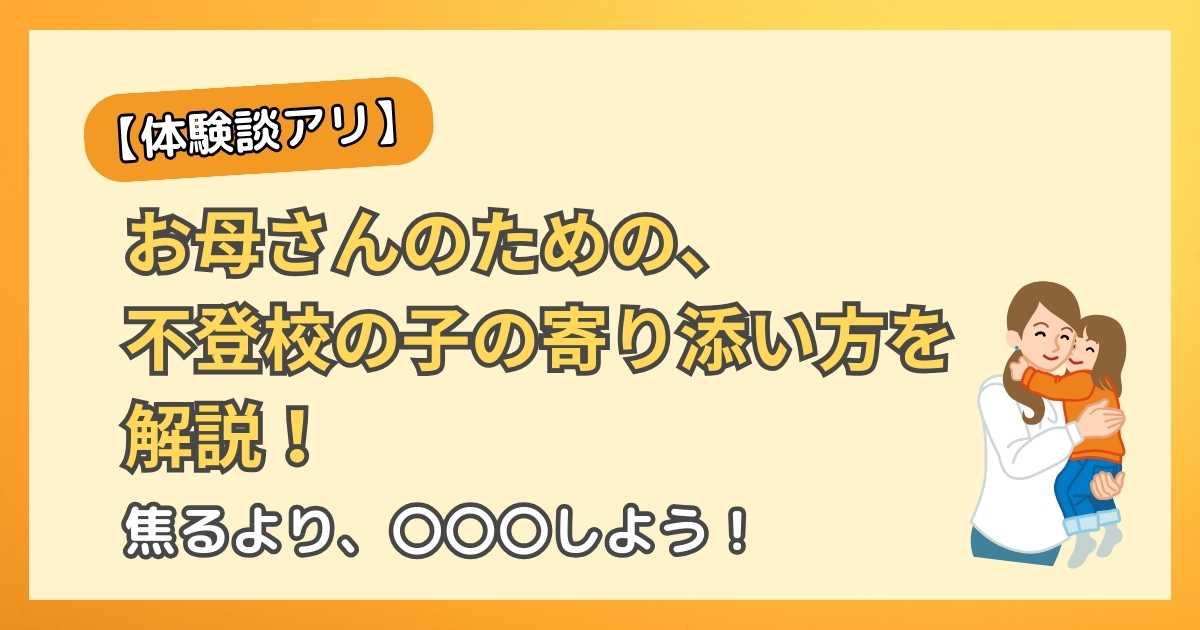【現役教員が解説】不登校を乗り越えるためにできることとは?家族で希望あふれる未来へ!

「うちの子、どうして学校に行けないんだろう…」
「家族の雰囲気がどんどん悪くなっていく気がする…」
不登校のお子さんを持つあなたは今、こんな風に悩んでいませんか?
この記事では、
こういった気づきが得られるはずです。
本ブログ「親子ウェルカムステーション」では、現役の学校の先生が執筆を担当しています。
現場での経験に基づいたリアルな視点と、不登校児童生徒や保護者向けのオンライン相談会で得た多くの声をもとに、記事作成しております。
実際に多くのご家族が抱える悩みに寄り添い、解決の糸口となる情報をお届けします。
ぜひ最後までこの記事を読んで、ご夫婦で子供の未来を考えるきっかけにしてください。記事へのコメントもお待ちしています。
また、定期的に無料相談会を開催しており、公式LINEでご相談を受け付けていますので、ぜひご登録ください
↓↓
家族の絆を深めることから始める

不登校は、子どもだけでなく、家族全体を巻き込む大きな問題です。
しかし、この困難な状況を乗り越えるために、家族の絆を深めることは、非常に重要です。家族の絆が深まれば、子どもはより安心して自分の気持ちを打ち明けやすくなり、家族全体で問題解決に取り組むことができます。
そのための具体的な方法として、以下の2つを示します。
① お互いの気持ちを聞き合う
家族の絆を深めるためには、お互いの気持ちをじっくりと聞き合うことが大切です。
そのためには、家族会議を開き、それぞれの思いや不安を共有する場を設けましょう。会議といっても、堅苦しい雰囲気ではなく、リビングや庭など、リラックスできる場所でお茶を飲みながらなど、アットホームな雰囲気で行うのが理想的です。
話し合いでは、相手の話を遮らず、最後までしっかりと聞くことを心がけることがいいです。
相槌を打ったり、「なるほど」と相づちを打つことで、相手は安心して話しやすくなります。さらに重要なのは、相手の言葉の裏にある感情に共感することです。「つらいね」「大変だったね」など、温かい言葉をかけ、気持ちに寄り添いましょう。
例えば、「学校に行きたくない気持ち、よくわかるよ。毎日学校に行くのは、大人だって大変なことだからね」のように、具体的な言葉で共感を示すことで、子供はより安心感を覚えるでしょう。
このように、温かい雰囲気の中でじっくりと互いの気持ちを伝え合うことが、家族の絆をより一層深めることに繋がります。
② 共感の言葉をかける
共感の言葉をかけることは、相手を認め、受け入れる上でとても大切です。
相手を認め、受け入れる上で非常に重要なのが、共感の言葉をかけることです。単に「そうだね」と言うだけでなく、「学校に行きたくない気持ち、よくわかるよ」のように、相手の気持ちを具体的に表現して共感を示すことです。
その際、「そんなことないよ」や「もっと頑張りなさい」といった否定的な言葉は避けましょう。これらの言葉は相手の気持ちを傷つけ、心を閉ざしてしまう可能性があります。
具体的には、「学校に行きたくない気持ちがあるんだね。どうしてそう思うのかな?」と、相手の気持ちを尊重し、問いかけるような言葉を選ぶようなイメージです。
このように、具体的な共感の言葉を選び、否定的な言葉を避け、子供の気持ちを尊重することで、より良いコミュニケーションを築き、互いの理解を深めることができるでしょう。
家族でできることを一緒に探そう

一緒にご飯を作る
ただ単にご飯を作るだけでなく、メニューを一緒に考えたり、食材の買い物に行ったりするのもおすすめです。料理を通して、協調性や達成感を味わうことができます。
例えば、「今日は何を作ろうか?」と子どもに意見を聞いたり、「この野菜を切るのを手伝ってくれる?」と役割分担をすることで、子どもは「自分は家族の一員として貢献している」と感じることができます。
また、食事の時間を家族みんなで囲むことで、コミュニケーションの機会が増え、絆が深まります。
散歩に出かける
近所の公園や自然豊かな場所へ散歩に出かけましょう。散歩中、道端の花や虫を観察したり、季節の変わりを感じたりすることで、五感を刺激し、心身のリフレッシュにつながります。
また、散歩中に見つけた面白いものについて話したり、ゲームを取り入れたりすることで、会話が弾み、家族の絆が深まります。
ゲームをする
ボードゲームやカードゲームなど、家族みんなで楽しめるゲームを選びましょう。ゲームを通して、協力することの大切さや、負け方、勝ち方を学ぶことができます。
また、ゲームをすることで、家族みんなで同じ時間を共有し、楽しい思い出を作ることができます。
ボランティア活動に参加する
地域清掃活動やフードバンクへの支援など、家族みんなで参加できるボランティア活動を探してみましょう。
ボランティア活動を通して、社会貢献の大切さを学び、他者への思いやりを育むことができます。また、共同で一つの目標に向かって活動することで、家族の絆が深まります。
これらの活動を通して、大切なのは、子どもが楽しんでいるかどうかです。
外部の力を借りることも大切

一人で抱え込まず、専門家や地域の支援団体に相談することも、不登校を乗り越える上で非常に大切です。
スクールカウンセラー
学校に配置されている専門の相談員です。お子様の学校生活での悩みや、人間関係のトラブルなど、学校に関連する問題全般について相談することができます。
スクールカウンセラーは、中立的な立場で、お子様の気持ちを聞き、具体的なアドバイスや解決策を提案してくれます。
児童相談所
児童福祉に関する専門機関です。不登校だけでなく、虐待、ネグレクトなど、子どもに関する様々な問題に対応しています。
児童相談所では、心理士やソーシャルワーカーが、お子様やご家族の状況を詳しく聞き、必要な支援につなげます。例えば、家庭訪問や児童福祉施設への入所、里親制度の紹介など、多様な支援を受けることができます。
地域の支援団体
地域には、不登校の子どもやその家族を支援する様々な団体があります。
NPO法人やボランティア団体などが運営している場合が多く、親の会や子ども向けのワークショップ、学習支援など、多様な活動を行っています。これらの団体では、同じような悩みを持つ他の親と交流したり、情報交換したりする機会も得られます。
まとめ

今回は、不登校の子をもつご家族の支えとなるよう、具体的な支援策を解説していきました。
ぜひ家族みんなで力を合わせ、お子さんのことを温かく見守り、支えてあげるエネルギーになれば幸いです。
また外部機関も惜しみなく頼ってください。
一緒に、お子さんの未来を考えていきましょう。コメントもお待ちしています。
Warning: Undefined array key 0 in /home/starseeker97/oyakowelst.com/public_html/wp-content/themes/jinr/include/shortcode.php on line 306