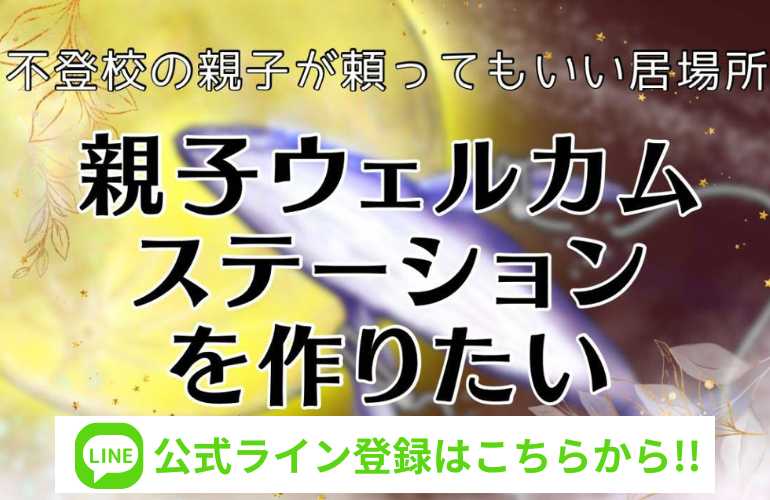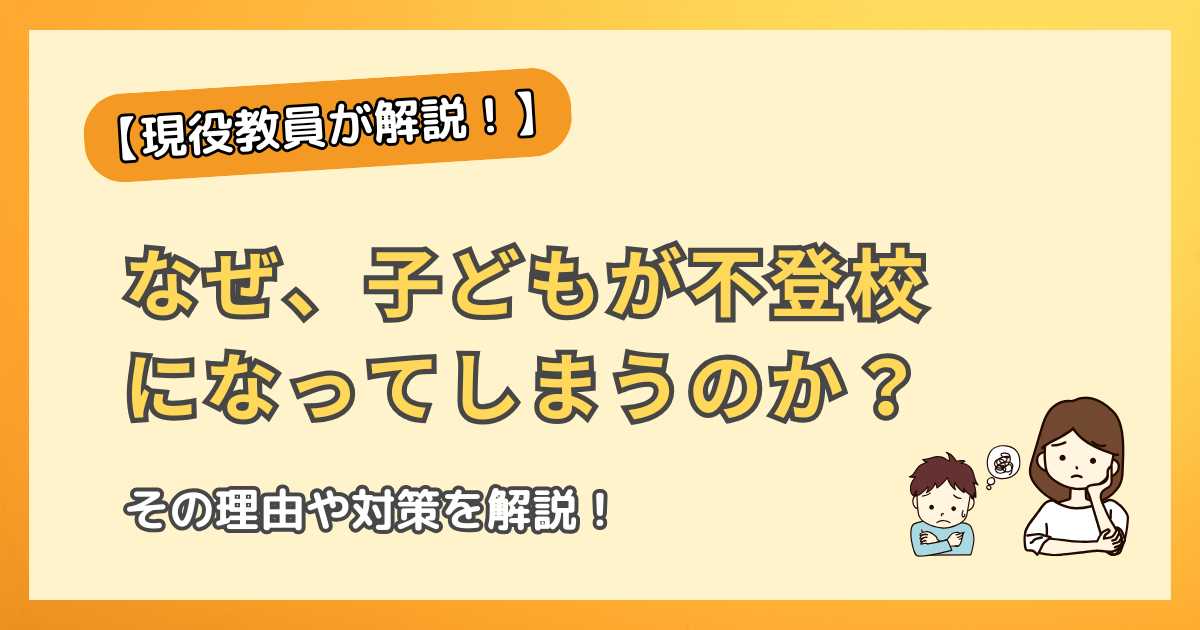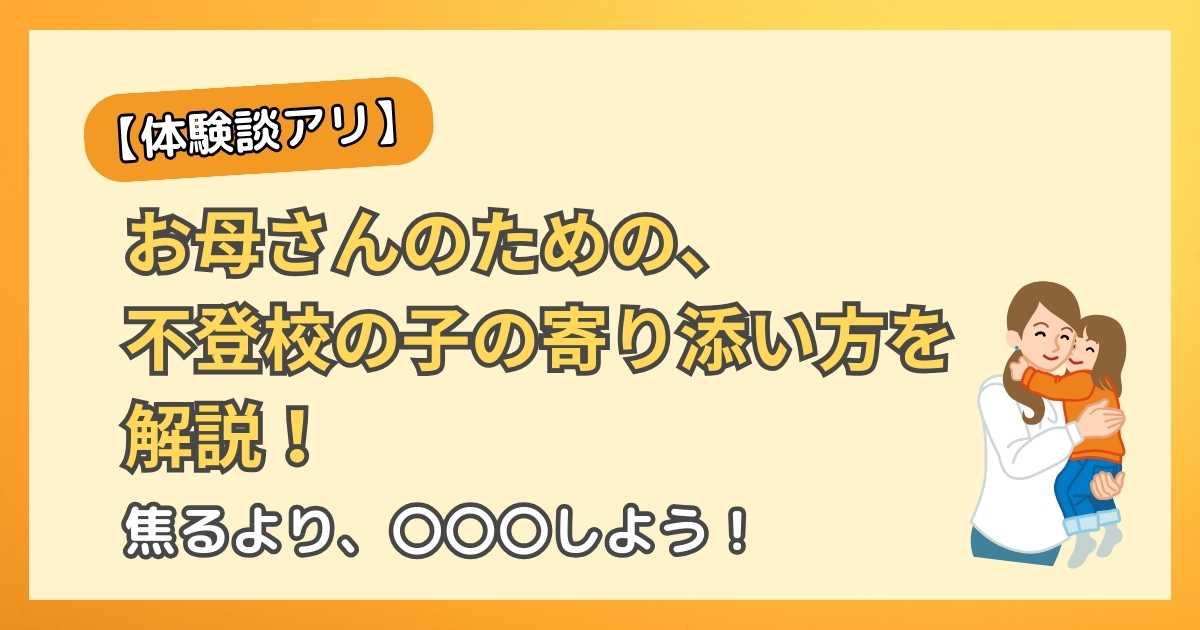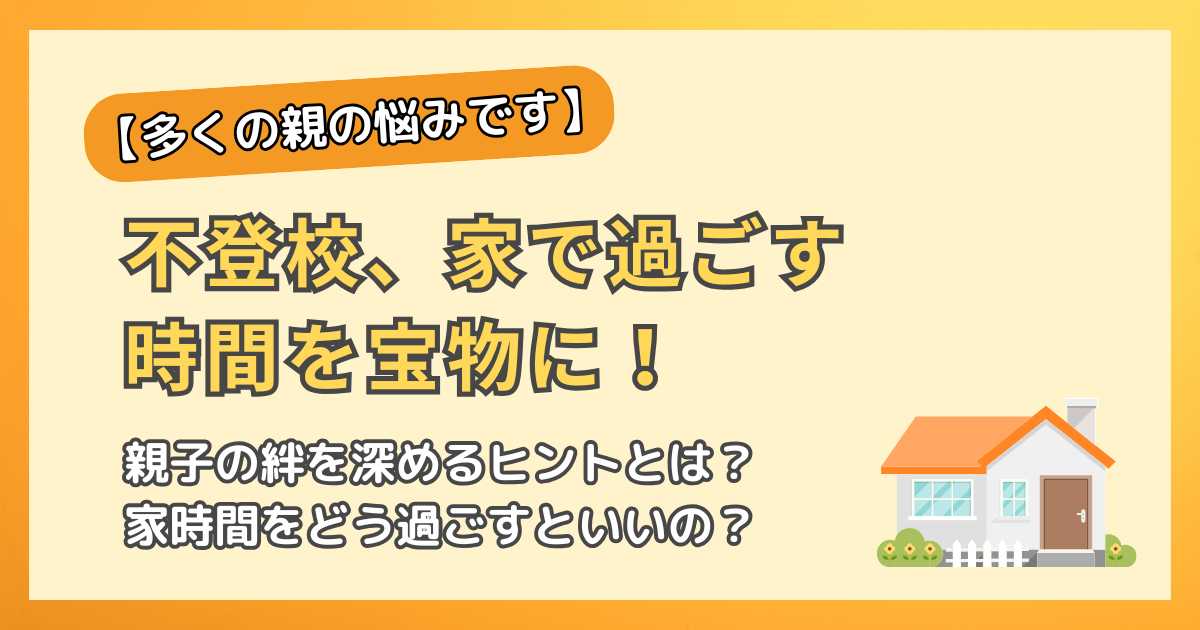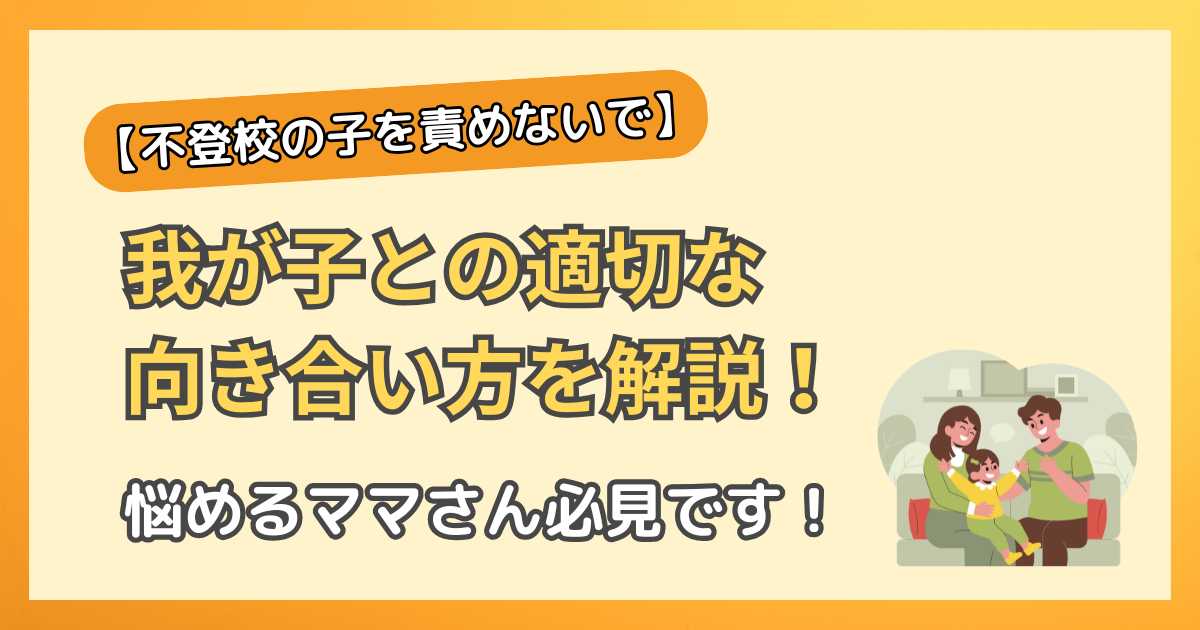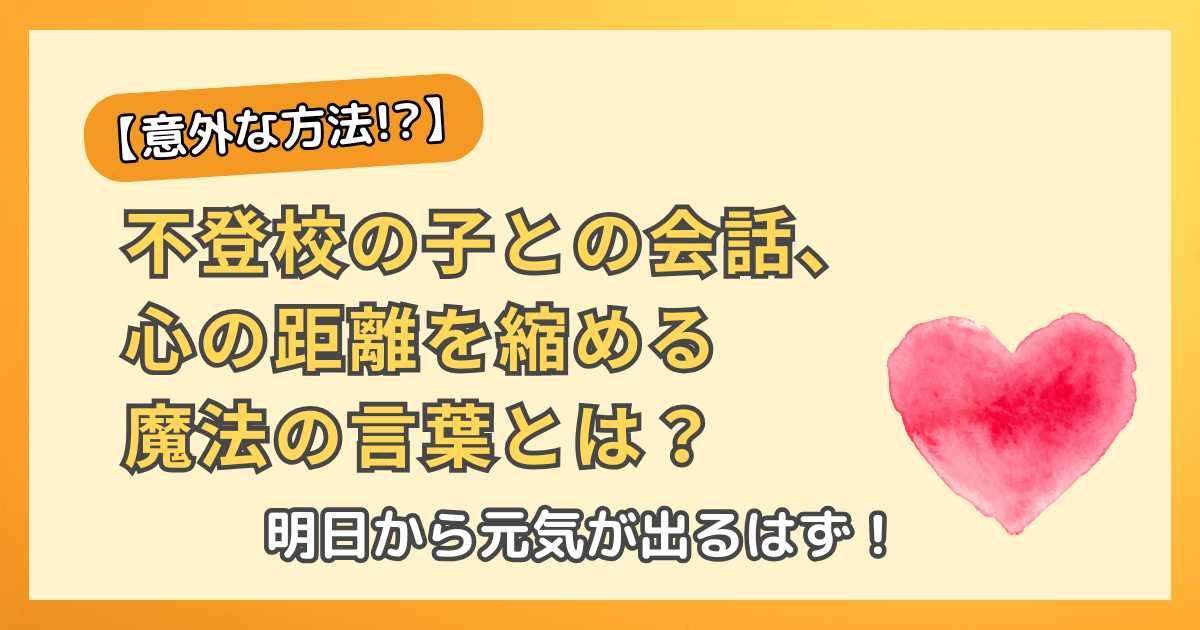発達障害の子が不登校になったら?「将来、仕事ができるのか問題」に役立つ情報を解説!
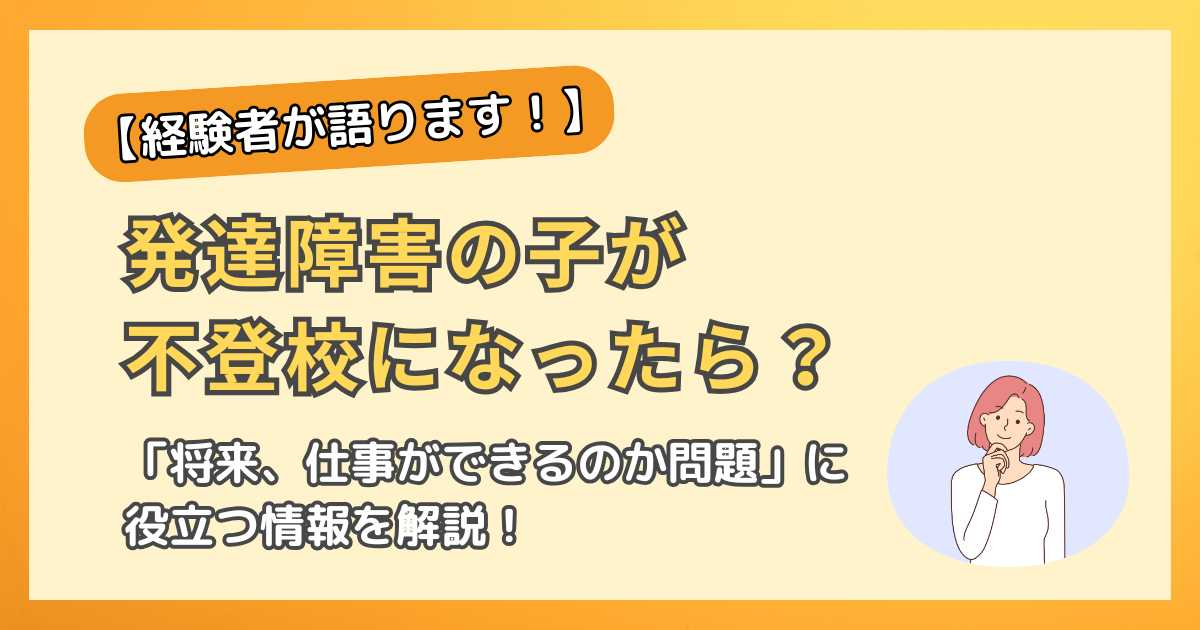
「このまま学校に行けなくなったら、進学や就職はどうなるのだろうか」
「社会で自立できるのだろうか」
この記事を見たあなたはこんな風に悩んでいませんか?
発達障害を抱えるお子さんの不登校は、保護者の方にとって複雑で深刻な悩みをもたらすことが多いです。
まず、お子さんの将来に対する強い不安があります。「社会で自立できるのだろうか」といった心配が常に頭から離れません。
「親の育て方が悪い」「甘やかしすぎだ」といった心無い言葉に傷つき、孤立感を深めてしまうこともあります。
さらに発達障害を抱えるお子さんの保護者様は、こんな疑問を感じるのではないでしょうか?
このような情報は、探しても意外と見つからないことが多いですよね。
この記事を読むと、
こういった気づきが得られるはずです。
本ブログ「親子ウェルカムステーション」では、現役の学校の先生が執筆を担当しています。現場での経験に基づいたリアルな視点と、不登校児童生徒や保護者向けのオンライン相談会で得た多くの声をもとに、記事作成しております。
今回は、就労移行支援サービスを利用し、2024年秋に在宅勤務形態で就職した「ゆめ」が記事を執筆させていただいております。
実際に多くのご家族が抱える悩みに寄り添い、解決の糸口となる情報をお届けします。
ぜひ最後までこの記事を読んで、お子供の未来を考えるきっかけにしてください。記事へのコメントもお待ちしています。
また、定期的に無料相談会を開催しており、公式LINEでご相談を受け付けていますので、ぜひご登録ください。
↓↓
不登校のお子さんの「働く」を支える就労支援サービスとは?

まずは、障害のあるお子さん向けの就労支援サービスについて、分かりやすく解説します。
1. 就労選択支援~お子さんに合った「働く」を一緒に見つける
「就労選択支援」は、2025年10月に開始される新しいサービスです。お子さんの希望や能力を丁寧に確認し、最適な就労支援サービスを一緒に探すことを目的としています。
以前は、お子さん自身や保護者の方がどのサービスを利用するかを決めて申請する必要がありましたが、必ずしもお子さんに合ったサービスを選択できるとは限りませんでした。しかし、就労選択支援では、専門家がお子さんの状況をしっかりと把握し、客観的な視点からアドバイスを行うため、ミスマッチを防ぎやすくなります。
具体的には、一定期間、作業体験や面談を通して、お子さんの得意なことや苦手なこと、希望する働き方などを確認します。その上で、就労継続支援や就労移行支援など、さまざまあるサービスの中から、お子さんに合ったものを提案します。
アセスメントと呼ばれるこの過程を通じて、お子さん自身の特性やニーズを深く理解し、適切な支援計画を立てることが可能になります。
「うちの子にはどんな働き方が合っているんだろう?」
「どのサービスを選べばいいか分からない」
と悩んでいる保護者の方にとって、心強いサポートとなるでしょう。また、このサービスは、お子さんが将来のキャリアについて考える良い機会にもなります。
2. 就労継続支援~働く場所とスキルアップの機会を提供
「就労継続支援」は、一般企業での就労が難しいお子さんに対して、働く場所とスキルアップの機会を提供するサービスです。A型とB型の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
①A型:雇用契約を結び、賃金をもらいながら働く
A型は、企業と雇用契約を結び、最低賃金が保証された賃金をもらいながら働きます。一般企業に近い形で働くため、就労に必要なスキルや生活リズムを身につけることができます。比較的安定した収入を得ながら、社会性を養うことができるのが特徴です。
②B型:雇用契約を結ばずに、工賃をもらいながら働く
B型は、雇用契約を結ばずに、作業量に応じた工賃をもらいながら働きます。A型に比べて、比較的ゆったりとしたペースで働くことができるため、体調やペースに不安があるお子さんでも安心して利用できます。
自分のペースで作業を進めながら、徐々に自信をつけていくことができます。
近年では、在宅で訓練や勤務ができる事業所も増えており、お子さんの状況に合わせて柔軟な働き方を選択できるようになってきています。これにより、通勤の負担を軽減したり、自宅で落ち着いて作業に取り組んだりすることが可能になります。
3. 就労移行支援~一般企業への就職をサポート
「就労移行支援」は、一般企業への就職を目指すお子さんに対して、必要な知識やスキルを身につけるための訓練を行うサービスです。原則2年間、専門家のサポートを受けながら、就職活動を進めます。
具体的には、ビジネスマナーやコミュニケーションスキル、PCスキルなどの訓練や、職場体験実習、就職後の定着支援などを行います。個々の能力や適性に合わせたカリキュラムが組まれ、専門のスタッフが一人ひとりを丁寧にサポートします。
就労移行支援は、就職に必要なスキルだけでなく、生活リズムを整えたり、体調を管理したりといった、社会人として必要な力を総合的に身につけることができるのが特徴です。また、履歴書の書き方や面接対策など、具体的な就職活動のサポートも行います。
ただし、利用できるのは原則1回のみで、学生の間は利用できません。
また、2年間の期間内に就職活動を行う必要があるため、お子さんによってはハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、集中的な訓練とサポートを通じて、一般企業への就職という目標に近づくことができます。
4. 就労定着支援~就職後の「働く」をサポート
「就労定着支援」は、就労継続支援や就労移行支援を利用して一般企業に就職したお子さんが、長く働き続けられるようにサポートするサービスです。
就職後6ヶ月から最大3年間、仕事や生活に関する相談に乗ったり、職場とのコミュニケーションを支援したりします。具体的には、定期的な面談や職場訪問を通じて、お子さんの状況を把握し、必要なアドバイスやサポートを行います。
就職はゴールではなく、スタートです。就職後に起こるさまざまな課題に対応しながら、お子さんが安心して働き続けられるように、就労定着支援は力強い味方となるでしょう。
例えば、職場での人間関係の悩みや、仕事の進め方に関する困りごとなど、さまざまな相談に対応します。
これらのサービスは、お子さんの状況や目標に合わせて、組み合わせて利用することも可能です。まずは、お住まいの地域の相談支援事業所に相談し、お子さんに合った支援を見つけていきましょう。
【定着支援後に活用!】就労を継続するためのサポートってあるの?

お子さんが就職し、定着支援も終了。しかし、その後も「職場で困ったことがあったらどうしよう」「長く働き続けられるだろうか」と、不安を感じる保護者の方もいらっしゃるかもしれません。
ここでは、定着支援終了後も利用できる支援サービスについて解説します。
1. 就ポツ(障害者就業・生活支援センター)
「就ポツ(障害者就業・生活支援センター)」は、就職を希望する障害のある方や、すでに働いている障害のある方に対して、就労と生活の両面から一体的なサポートを行う機関です。
定着支援が終了した後も、職場での悩みや困りごと、生活上の課題など、さまざまな相談に乗ってもらえます。専門のスタッフが、お子さんの状況に合わせて、適切なアドバイスや支援を提供します。
就ポツでは、以下のようなサポートを受けることができます。
✅就労に関する相談
・職場での人間関係の悩み
・仕事の進め方に関する困りごと
・キャリアアップに関する相談
✅生活に関する相談
・日常生活の困りごと
・金銭管理に関する相談
・健康管理に関する相談
✅作業評価
得意な作業や苦手な傾向を知るための評価(ただし、視覚障害がある場合は受けられないことがあります)
就ポツは、お子さんが長く安心して働き続けるための、心強い味方となるでしょう。ただし、支援内容は自治体や運営団体によって異なるため、事前に確認することをおすすめします。
2. ハローワーク
ハローワークは、求職者に対して職業紹介や就職支援を行う機関ですが、障害のある方の就労支援にも力を入れています。
ハローワークの紹介で就職した場合、就職後に職場や雇用に関するトラブルが発生した際には、相談に乗ってもらうことができます。例えば、以下のようなケースが考えられます。
・労働条件に関するトラブル
・職場での差別やハラスメント
・解雇に関するトラブル
ハローワークには、専門の相談員がおり、法律や制度に基づいて、適切なアドバイスや解決策を提案します。
また、ハローワークでは、障害のある方向けの求人情報も提供しています。定着支援終了後も、キャリアアップを目指したり、転職を検討したりする際に、活用することができます。
ハローワークは、全国各地に設置されており、相談は無料です。困ったことがあれば、気軽に相談してみましょう。
これらの支援機関は、お子さんが社会に出てからも、安心して働き続けられるようにサポートしてくれる存在です。困ったときには、一人で悩まずに、ぜひ相談してみてください。
【意外と知られてない】なんか困ったら相談支援事業所を頼るべし!

「どんな支援があるのか分からない」
「支援の利用対象なのか分からない」
「利用申請の出し方が分からない」
とにかくあらゆる場面で分からないことが出てくると思います。
そんなときにおススメなのが、相談支援事業所です!
相談支援事業所は、障害のある本人や家族の相談にのる機関で、診断がすでに出ていて何かに困っていれば、活用することができます。
相談支援事業所ってどんなところ?
Q1.どんな相談に乗ってくれるの?
・利用できる支援サービスについて知りたい
・サービスの利用方法が分からない
・お子さんに合った支援計画を立てたい
・学校や他の機関との連携について相談したい
・日常生活での困りごと
Q2.どんな人が相談に乗ってくれるの?
・相談支援専門員という、専門的な知識と経験を持つスタッフが対応します。
Q3.どこにあるの?
・お住まいの地域にある相談支援事業所を探すことができます。お住まいの市区町村の障害福祉課にお問い合わせください。
Q4.どうやって相談するの?
・電話やメールで相談の予約をします。
・相談支援事業所を訪問して相談します。
・自宅や指定した場所に来てもらって相談することも可能です。
相談支援事業所を利用するメリット
✅さまざまな関係機関との連携をサポート
相談支援専門員が、学校や医療機関、就労支援機関など、関係機関との連絡調整を行ってくれます。
これにより、保護者の方の負担を大幅に軽減することができます。
✅自宅での相談も可能
外出が難しい場合や、相談支援事業所まで距離がある場合でも、自宅で相談することができます。
✅継続的なサポート
・サービスの利用開始後も、定期的に相談に乗ってもらえます。
・困ったことがあれば、いつでも相談できるので安心です。
サービス利用の流れ
1.相談:
まずは、相談支援事業所に連絡して、相談内容や困りごとを伝えましょう。
2.相談支援専門員との面談:
相談支援専門員が、お子さんの状況や希望を詳しく聞き取り、どのような支援が必要かを一緒に考えます。
3.サービス等利用計画案の作成:
面談内容に基づいて、どのようなサービスを利用するか、具体的な計画を立てます。
4.支給決定:
市区町村が、計画に基づいてサービスの利用を決定します。
5.個別支援計画の作成:
利用するサービスを提供する事業所と、具体的な支援内容や目標を定めた計画を作成します。
6.モニタリング:
定期的に相談支援専門員が、サービスの利用状況や効果を確認し、必要に応じて計画の見直しを行います。
障害者手帳とは?取得するとどんなメリットがあるの?

ここまで様々な支援サービスについてお話してきましたが、最後は障害者手帳について解説をします。
というのも、適切な支援を受けるためには、この手帳が非常に大きな役割を果たすことがあります!
「まだ手帳を持つほどではない」「周りの目が気になる」とためらう方もいるかもしれません。これから紹介することを参考にしつつ、1つの選択肢として活用の検討をしてくださいね。
そもそも障害者手帳とは?
障害者手帳は、障害のある方が各種福祉サービスを利用するために必要な証明書です。手帳の種類は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、発達障害の場合は主に精神障害者保健福祉手帳が対象となります。
よく聞く質問の1つに、
「手帳がなくてもサービスは利用できるのですか?」
があります。
障害福祉サービスを利用するためには「障害福祉サービス受給者証」が必要で、これは手帳がなくても取得可能です。
しかし、手帳がない場合は、障害や疾患を証明する書類(医師の診断書や障害年金の受給証明など)が必要となり、手続きに時間と手間がかかります。
手帳取得の3つのメリットを紹介!
①スムーズなサービス利用:
・手帳があれば、各種福祉サービスをスムーズに利用できます。
・就労支援や日常生活のサポートなど、必要な支援を受けやすくなります。
②経済的な支援:
・手帳の種類や等級によっては、税金の控除や公共交通機関の割引など、経済的な支援を受けられます。
③就職活動での配慮:
・障害者雇用枠での就職活動が可能になり、企業からの理解や配慮を得やすくなります。
そして、手帳取得には注意点もあります。
精神障害者保健福祉手帳の場合、初診から半年経過しないと申請できません。
また、精神科や心療内科は予約が取りにくく、待ち時間が長い場合があります。
申請から交付まで時間がかかることが多く、1ヶ月以上かかるのが一般的だということを覚えておきましょう。
【重要】早めの申請を強くオススメします!
学校生活で問題なく過ごせていても、就職後に適切な支援を受けられず苦労するケースは少なくありません。手続きに時間がかかることも考慮し、特性が強く出ていたり、診断を受けていたりする場合は、早めの申請を強くお勧めします。
年齢が若いうちに適切な支援を受けることは、お子さんの将来を大きく左右します。周囲の無理解や支援不足は、お子さんの心を深く傷つけ、自己肯定感を低下させる可能性があります。
「若いから大丈夫」「昔はこんなものなかった」という言葉で、必要な支援から目を背けるべきではありません。
私自身、必要な時に適切な支援を受けられなかった経験から、同じような思いをするお子さんが一人でも減ることを心から願っています。
まとめ~支援を上手く活用して将来への不安を少なくしよう!~

いかがでしたでしょうか?
今回は、発達障害を抱えるお子さんの不登校という状況に寄り添い、将来の就労に向けた具体的な支援策を紹介していきました。
就労選択支援から就労定着支援、そして定着支援後の就ポツやハローワークの活用まで、段階に応じた支援サービスがあることや、相談支援事業所の役割や障害者手帳の取得について詳しく述べてきましたので、分からなかった箇所は繰り返し見返すようにしてくださいね。
お子さんの将来を真剣に考える保護者の方々にとって、希望の光となる情報源になれば嬉しいです!
最後まで見てくださってありがとうございました。コメントもぜひお待ちしています!
Warning: Undefined array key 0 in /home/starseeker97/oyakowelst.com/public_html/wp-content/themes/jinr/include/shortcode.php on line 306