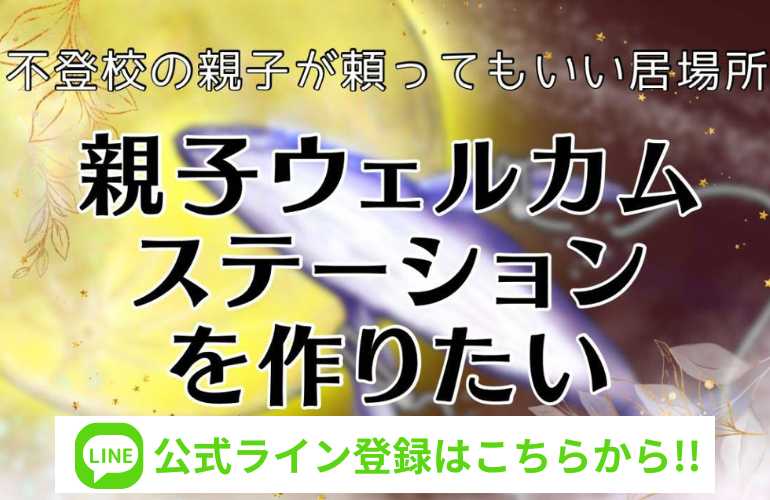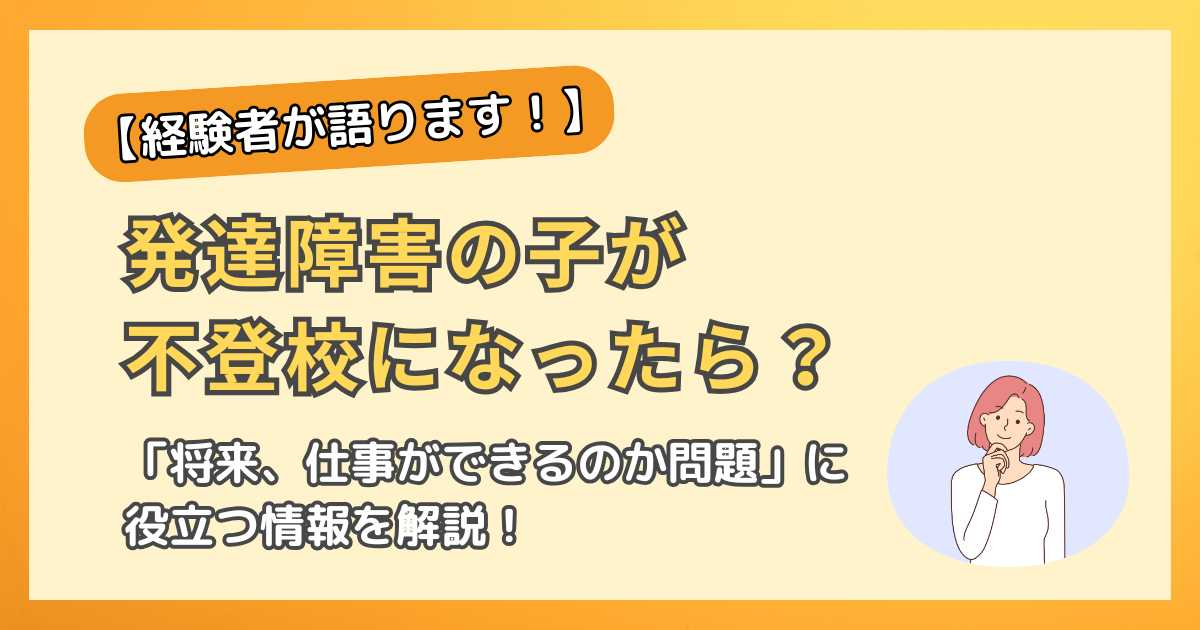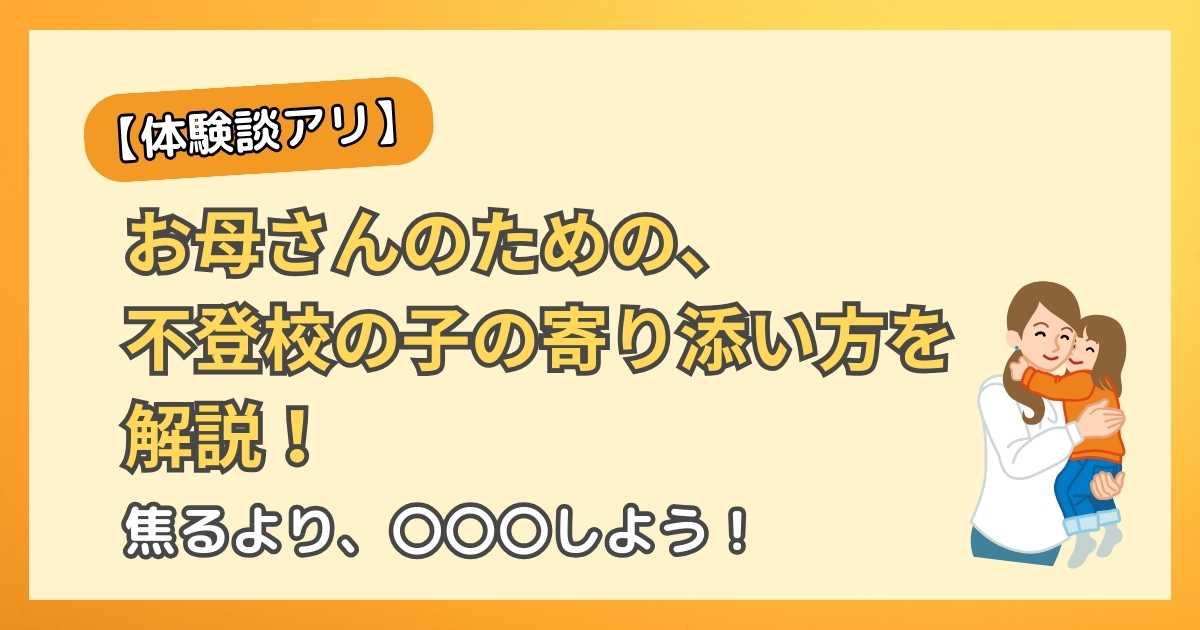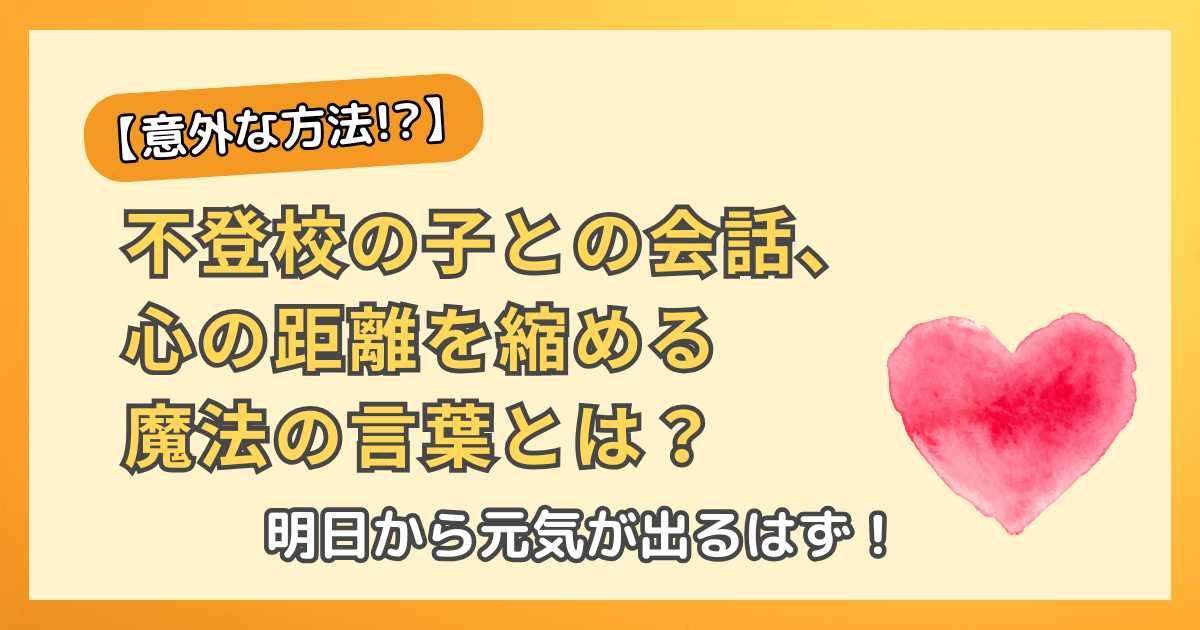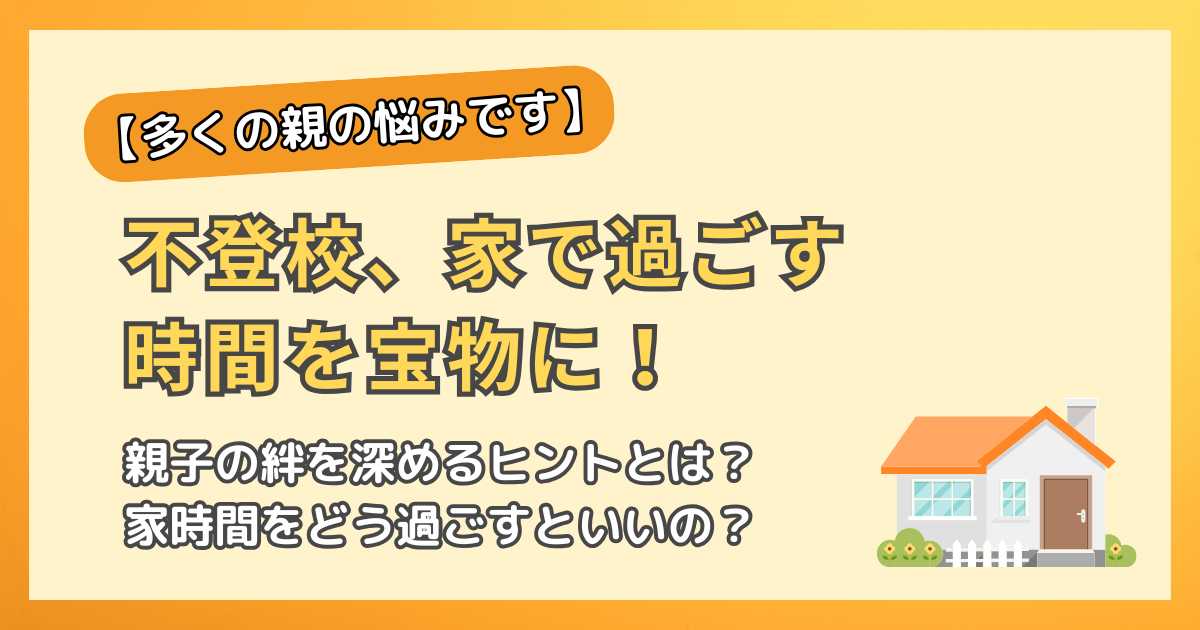【現役教員が解説!】なぜ、子どもが不登校になってしまうのか?その理由や対策を解説!
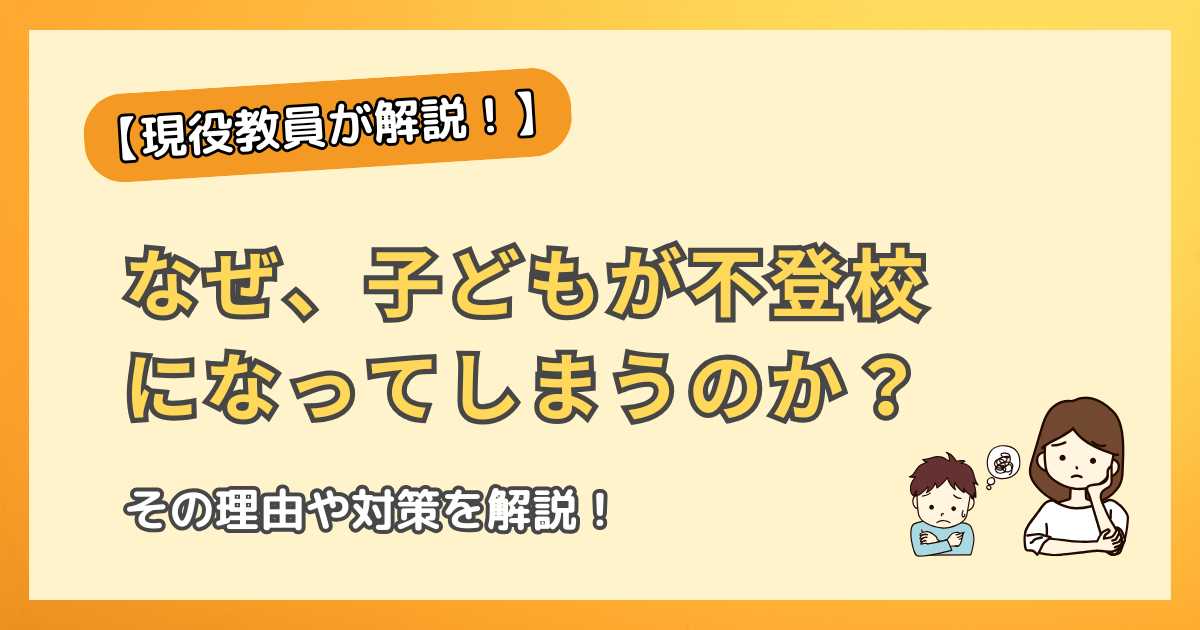
この記事を読んでいるあなたは、お子さんの不登校について、
「うちの子は一体なぜ学校に行かないんだろう?」
「何か私たちが悪かったんだろうか?」
と、理由が分からず、不安や焦りを感じているかもしれません。
お子さんが学校に行かない理由は、一概には言えず、複雑に絡み合っている場合がほとんどです。
この記事では、不登校の理由について、現役教師の視点から詳しく解説していきます。
この記事を読むことで、
といった気づきが得られるはずです。
お子様の不登校という状況に、少しでも光を灯せるよう、心を込めて解説していきます。
本ブログ「親子ウェルカムステーション」では、現役の学校の先生が執筆を担当しています。
現場での経験と、不登校児童生徒や保護者向けのオンライン相談会で得た多くの声をもとに、記事を作成しています。
多くのご家族が抱える悩みに寄り添い、解決の糸口となる情報をお届けします。
ぜひ最後までこの記事を読んで、お子様の気持ちを理解し、寄り添うための一歩を踏み出してください。
また、定期的に無料相談会を開催しており、公式LINEでご相談を受け付けていますので、ぜひご登録ください。
↓↓
そもそも「不登校」ってどんな状態?
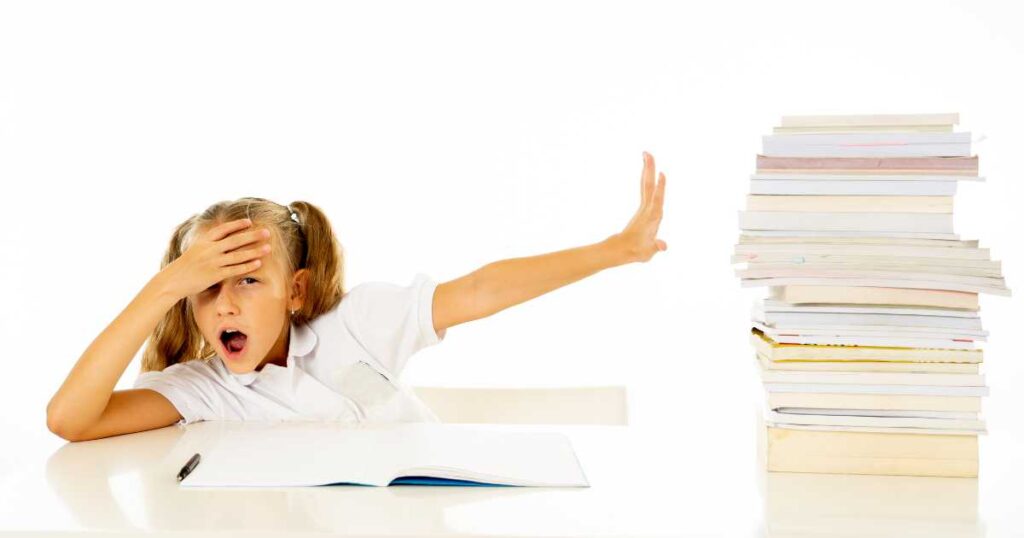
まず、「不登校」がどのような状態を指すのか、明確にしておきましょう。
文部科学省では、不登校を以下のように定義しています。
”相当の期間学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担その他の事由のために就学が困難である状況として文部科学大臣が定める状況にあると認められるもの”
参考資料:児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査-用語の解説
また、年間30日以上欠席し、病気や経済的な理由などの「やむを得ない」理由ではなく、心理的・情緒的要因や家庭・学校にかかわる要因などによって欠席している場合を「不登校」と定義しています。
しかし、実際には「何日休んだから不登校」と明確に決まっているわけではなく、お子様の置かれている状況や背景を総合的に考える必要があります。
また、不登校は以下のような状態も含まれます。
・友人関係又は教職員との関係に課題を抱えているため登校しない(できない)。
・遊ぶためや非行グループに入っていることなどのため登校しない。
・無気力で何となく登校しない。迎えに行ったり強く催促したりすると登校するが長続きしない。
【不登校の理由】不登校になる理由は一つじゃない!

お子様が不登校になる理由は、決して一つではありません。様々な要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。
ここでは、不登校の理由としてよく挙げられるものをいくつか紹介します。
1. 心理・情緒的要因
・学校や勉強、人間関係に対する不安・恐怖・緊張
・自己肯定感の低下や抑うつ状態、ストレス
・発達特性によるコミュニケーションや環境適応の難しさ
2. 家庭環境にかかわる要因
・家族との関係の変化(不和、虐待など)
・過保護・過干渉や逆に放任など、家庭内の教育方針の影響
・保護者の離職・転職・転居など生活環境の大きな変化
3. 学校環境にかかわる要因
・いじめや友人関係のトラブル
・学業の過度な負担・プレッシャー(受験・成績など)
・教員との関係が合わない、学校の制度やルールへの違和感
4. 社会的要因
・外的環境の急激な変化(地域移動や新型感染症の流行等)
・SNSやインターネット環境の影響
・メディアからの情報や周囲の価値観に対する違和感
これらの要因が複合的に絡み合って不登校になるケースが少なくありません。
どんなメカニズムで不登校になるのか?

では、お子様はどのようなメカニズムで不登校に至るのでしょうか?
1. ストレス要因の蓄積
学校での勉強や人間関係、家庭環境など、日常的に小さなストレスが積み重なってきます。
子ども自身がこういったストレスに対処しきれなくなると、心身に不調が生じてしまいます。
2. 心身の反応(不安・恐怖など)の増幅
不登校のきっかけは、たとえば「朝起きられなくなった」「授業についていけない」「友達とうまくいかない」など、些細なことも含まれます。
そして、一度休むことでさらに「行きづらさ」が強化され、行かなかったことへの罪悪感や周囲の視線への恐怖心が増幅しやすくなる傾向があります。
3. 悪循環の形成
その後、学校を休む→周囲からの遅れや反応が気になる→さらに行きづらい→休みが続く、という悪循環に陥ってきます。
家庭でも「明日こそは行ってほしい」「何で行かないの?」というプレッシャーがかかることで、より一層行きづらくなることも多いです。
4. 長期化による孤立感や自己肯定感の低下
長期間の欠席で友達とのつながりが薄れ、孤立感や自己否定感が強まってしまいます。
これによって、さらに登校のハードルが高くなることでしょう。
このように、一度行きづらさを感じると、それがさらなる不安やストレスを呼び、行かない(行けない)ことに対する罪悪感などが重なり合って状態が長引くことがあります。
一度不登校になると、もう学校には戻れないのか?

結論、そんなことはありません。 不登校の状態から再登校するケースは多くあります。
ただし、再登校するまでに時間がかかったり、支援や環境調整が必要になったりすることがあります。カウンセリングやスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの活用、フリースクールや通信制高校への転校など、状況に応じてさまざまなサポートの形があります。
不登校をきっかけに、別の進路を選んだり、通信教育やインターネット学習を活用して学び続けたりする子どももいます。
また、不登校は悪いことなのかという悩みを自然と抱きがちですが、不登校は悪ではありません。
どんな子どもにも起こる可能性があります。
不登校は「子ども自身に何らかのサインが表れている状態」として捉えられることが多いです。
社会通念上、「学校に行かない(行けない)」ことはネガティブにとらえられがちですが、不登校を経験した人が全員、人生で失敗するわけでも、将来が閉ざされるわけでもありません。
実際、無理に登校を続けることで精神的に追い込まれてしまい、より深刻な心身の不調を引き起こすこともあります。
大切なのは、不登校という状態に陥っている背景や子どもの気持ちを理解し、必要なサポートや環境調整を行うことです。
まとめ~不登校は誰にでも起こる可能性がある!適切な対策を!~

この記事では、不登校の理由について詳しく解説しました。
お子様の不登校は、決して珍しいことではありません。
大切なのは、お子様の気持ちを理解し、寄り添い、必要なサポートをしていくことです。
この記事が、お子様の不登校で悩んでいるあなたの、少しでもお役に立てれば幸いです。
もし、もっと詳しく話を聞きたい、個別に相談したいという場合は、当ブログの公式LINEで個別相談を受け付けております。ぜひ気軽にご活用くださいませ。
一人で悩まず、私たちと一緒に、お子様の未来を考えていきましょう!
最後まで見てくださってありがとうございました。コメントもぜひお待ちしています!
Warning: Undefined array key 0 in /home/starseeker97/oyakowelst.com/public_html/wp-content/themes/jinr/include/shortcode.php on line 306